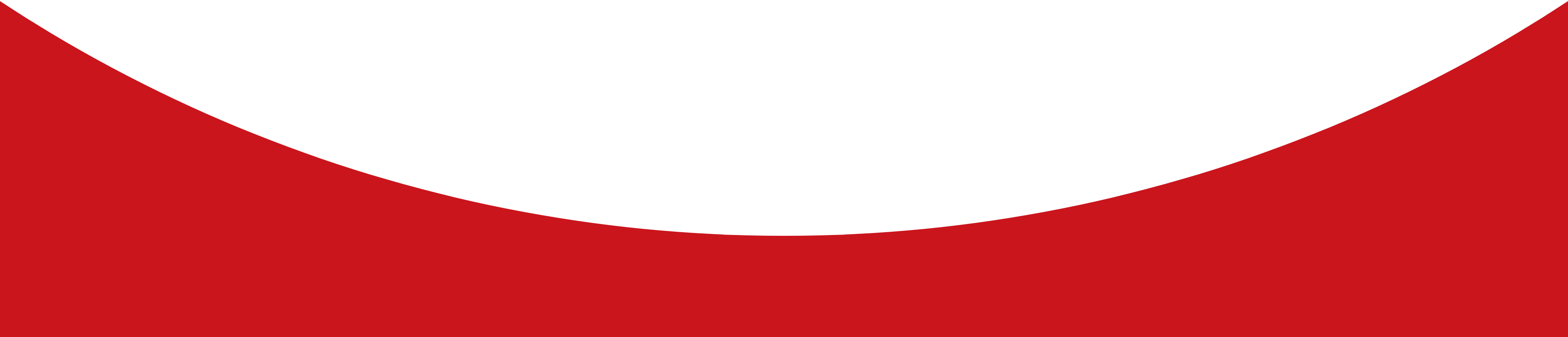熱きピッツァ職人との出会いから始まったチャレンジ

江別製粉株式会社 常務取締役
山口 小百合 氏
北海道では「きたほなみ」「ゆめちから」「キタノカオリ」「春よ恋」「はるきらり」「ハルユタカ」など様々な品種の小麦が生産されています。弊社ではそれぞれの小麦が持つ特性を活かし、パン用、麺用、菓子用と用途に応じて製粉し、全国のお客様にお届けしています。ピッツァ専用粉の開発は、東京の石神井町でイタリアンレストラン「ピッツェリア ジターリア ダ フィリッポ」を営むピッツァ職人の岩澤さんとの出会いから始まりました。
だけるようになりました。そんなこともあって、岩澤さんはそのピッツァ専用粉をイタリアの世界大会に持参し、意気揚々とピッツァを焼いたそうです。ところが、審査員から「あなたのピッツァは素晴らしいが、使用した小麦粉が『ピッツァナポレターナSTG』(以下、STG)の基準から外れているので失格です。」と告げられたそうです。日本に帰ってきた岩澤さんから、すぐに連絡が来ました。「STG規格をクリアするピッツァ専用粉を作ってください。来年の大会までに。」ここからでしたね、本当の意味でのチャレンジが始まったのは。

クリアするのは今まで見たことも
聞いたこともない基準
そもそも弊社にはSTG規格を知っている社員が一人もおらず、「STG って何?」そんなゼロからのスタートでした。解説本やインターネットの情報を頼りに、製品開発や営業、製造など各部の社員が集まって、STG規格を理解するところから始めました。「ピッツァナポレターナSTG」は、ナポリピッツァの伝統を守るため、製造方法や使用する食材などが定められていて、小麦粉に関しても規約の中に仕様が記載されていました。蛋白やフォーリングナンバーといった馴染みのある項目に並んで、W値やP/L値といった、生地の強さや伸展性のバランスを表す項目があり、これを見た時には正直なところ途方に暮れました。弊社にはその値を測る装置(アルベオグラフ)がなく、弊社の既存製品がどのくらいの値なのか、STGの仕様と近いのか遠いのか、それすら見当がつきません。まずはその装置を有し、粉の分析をしてくれるところはないかと関係者に尋ね回り、東京西葛西の「日本パン技術研究所」に年代物のアルベオグラフがあるという情報に辿り着きました。すぐに東京に出向き、週に一日だけならという条件で分析をお願いできることになりました。岩澤さんのお電話を受けてからすでに数週間が経過していました。
力強く背中を押してくれた
国と協会の補助事業
いざ始めてみるとSTGの仕様をすべて満たすという課題は簡単ではありませんでした。北海道産小麦粉を何種類か配合し、数値を測る、はみ出す項目があるので配合割合を変えてみる、うまくいかないのでもとの粉を変えてみる、といったことを繰り返し、少しずつ数値を寄せていきました。そして、作った粉は岩澤さんのほか、協力してくれる何人かのピッツァ職人に送り、お店で焼いて食べてもらいました。たとえ数値がクリアできても、美味しいピッツァが焼けない粉では意味がありませんから。食味、食感、作業性…ピッツァ専用粉に求められる要件とSTGの仕様を両立させるため、延々と試行錯誤を重ねました。
支えになったのは、全国米麦改良協会から紹介された国の補助事業でした。「北海道の小麦だけで、ナポリピッツァの国際規約に則った粉を作る」そんな無謀とも言える挑戦を、国が応援してくれていると思うと勇気が出ました。期限内に必ずやり遂げなければならないというプレッシャーも、良い方向に作用しました。ようやくこれはいけそうだという試作品を携え、岩澤さんはじめ関係者でイタリアに飛び立てたのも補助事業のおかげです。前年に岩澤さんが失格したピッツァ選手権の審査委員長が教鞭をとるピッツァ職人養成学校を訪ね、持ち込んだ試作品でピッツァを焼いていただきました。分析数値も見ていただきました。著名なピッツァ職人でもある先生から「この粉、美味しいね」「この粉での大会出場はもちろんOKだよ」とお墨付きをいただけたことは、その後の事業展開をする上で大きな自信につながりました。
「美味しそう」と思ってもらえるものにしたいと、初めてフルカラーのグラビア印刷を採用し、ピッツァのイラストを袋いっぱいに描きました。また、「海外の職人にも北海道の小麦を知ってもらいたい」との願いから「100% HOKKAIDO」とローマ字でロゴを入れました。今ではお使いいただいているお客様から、店内に積んでおくだけで絵になると喜んでいただいています。

地域に根差した江別製粉ならではの取り組みを、これからも
弊社では30年以上前から生産地に近い地の利を活かし、北海道産小麦を100%使った製品作りに挑み続けてきました。今回のピッツァ専用粉もそんなチャレンジの成果の一つです。ご
存知のように、小麦は粒のままでも、小麦粉のままでも食べられません。生産者、集荷団体、製粉会社、そして麵やパン、ピッツァなどに仕上げる職人の方々が揃って、やっとおいしくいただける作物です。製粉会社は生産者の方々と職人や消費者の方々との間に立つポジションであり、だからこそ、作る人、使う人、食べる人、それぞれの声に耳を傾けることも、それぞれに思いを届けることもできます。経営理念にもあるように「農」と「食」の現場に積極的に関わり、ともに課題に取り組み、喜びを分かち合う中で、北海道産小麦の価値を知っていただく。その積み重ねの先に、北海道産小麦のさらなる利用拡大があると信じています。
弊社には、原料小麦1トンから製粉できる小ロットプラントがあり、地域や生産者を限定した小麦粉の生産を可能にしています。これも生産者や消費者との対話の中から生まれたものです。このプラントを活用することで、農作物としての小麦を身近に感じる人が増え、生産現場と食卓との距離を縮めていけたらと考えています。小麦畑のすぐ近く、江別の地で75年。これからも北海道産小麦と向き合い、その魅力を最大限に引き出す製品作りで、世界に北海道産小麦の素晴らしさを発信していきたいと思います。

江別製粉本社(右側の建物が製造施設)